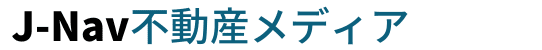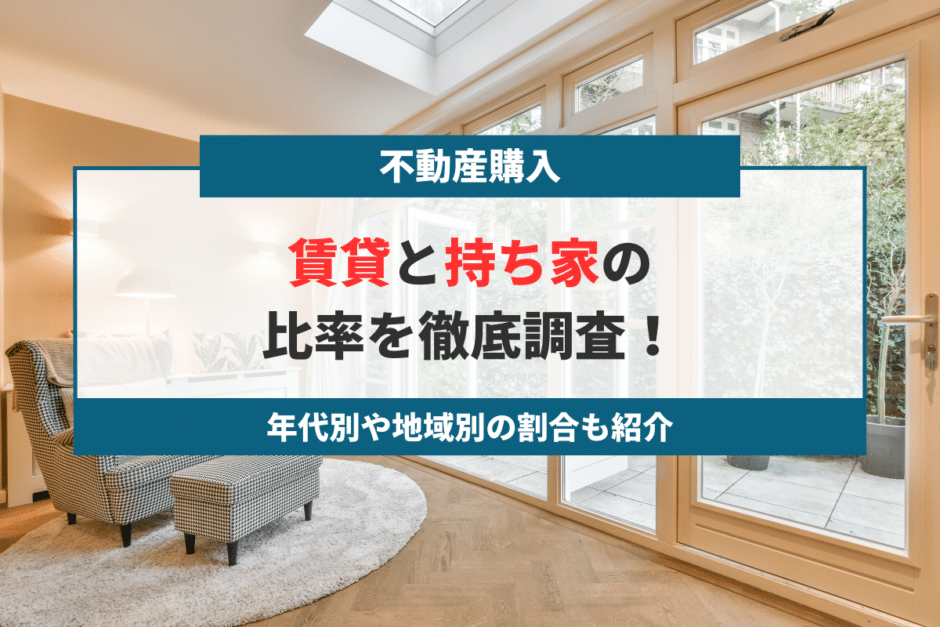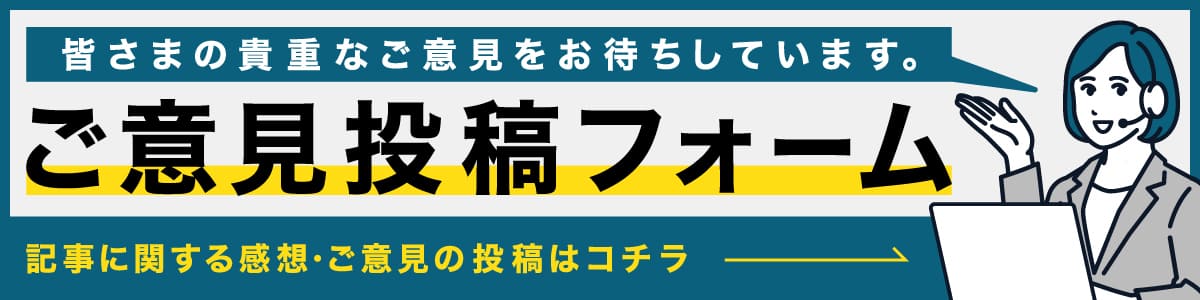家の購入は、これからの人生を左右する大きな決断です。住宅ローンを組めば、返済に数十年かかるのは珍しくありません。しかし、賃貸では一生家賃の負担が続くため、持ち家を手に入れるか迷ってしまいます。実際、賃貸と持ち家の比率はどのようになっているのでしょうか。
そこで本記事では、賃貸と持ち家の比率について、統計データやそこから見えてくる社会情勢、両者を比較するポイントを解説。ぜひ参考にして、これからの住まいで後悔のない選択をしましょう。
目次
賃貸と持ち家の比率の統計
賃貸と持ち家の比率について、年代や年齢、地域別の違いを統計データを元に解説していきます。あくまでこれまでの傾向ですので、今後はどうなるかわかりません。
賃貸と持ち家の比率は約4対6
総務省統計局が5年に1度発表している「住宅・土地統計調査」のデータをもとに、賃貸と持ち家の比率をみていきましょう。
2023年9月時点で最新の統計データである2018年の調査結果をみると、賃貸と持ち家の比率は約4対6です。1973年からの全国推移は次のようになっています。
| 年代 | 持ち家の戸数(千戸) | 賃貸(千戸) | 持ち家率 |
| 1973年 | 17,007 | 11,724 | 59.2% |
| 1978年 | 19,482 | 12,689 | 60.4% |
| 1983年 | 21,650 | 12,951 | 62.4% |
| 1988年 | 22,948 | 14,015 | 61.3% |
| 1993年 | 24,376 | 15,691 | 59.8% |
| 1998年 | 26,468 | 16,730 | 60.3% |
| 2003年 | 28,666 | 17,166 | 61.2% |
| 2008年 | 30,316 | 17,770 | 61.1% |
| 2013年 | 32,166 | 18,519 | 61.7% |
| 2018年 | 32,802 | 19,065 | 61.2% |
“参考:総務省統計局「平成30年 住宅・土地統計調査結果」”
賃貸には民営のものだけでなく、公営や公社のものも含まれています。賃貸も持ち家も総戸数は増加していますが、比率は35年間の統計データで大きくかわっていません。
年齢が上がるほど持ち家の比率は上昇
年齢別の持ち家の比率は、次のように推移しています。
| 年代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 |
| 1983年 | 17.9% | 53.3% | 71.0% | 78.8% | 77.6% |
| 1988年 | 12.1% | 49.6% | 69.0% | 77.3% | 78.6% |
| 1993年 | 8.4% | 43.0% | 67.4% | 75.6% | 79.8% |
| 1998年 | 8.1% | 39.4% | 67.0% | 75.1% | 80.5% |
| 2003年 | 8.2% | 38.3% | 65.6% | 75.1% | 80.0% |
| 2008年 | 7.5% | 39.0% | 62.7% | 74.6% | 80.2% |
| 2013年 | 7.8% | 38.8% | 59.6% | 71.7% | 80.0% |
| 2018年 | 6.4% | 35.9% | 57.9% | 67.9% | 80.0% |
“参考:厚生労働省「図表1-8-6 持家世帯比率の推移(家計を主に支える者の年齢階級別)」”
基本的に高齢になるほど持ち家の比率は高まる傾向です。両親などから相続・贈与された家に住むケースもあるため、独身でも持ち家の可能性はあります。調査対象を2人以上の世帯に絞り込むと、持ち家の比率はさらに高くなります。
東北の日本海側は持ち家比率が高い
地域ごとの持ち家の比率は次のようになっています。
| 持ち家の比率 | 都道府県 |
| 73.0%~ | 秋田・山形・新潟・富山・岐阜・福井・奈良・和歌山 |
| 68.0~72.9% | 青森・岩手・茨城・栃木・群馬・長野・石川・山梨・滋賀・三重・鳥取・島根・香川・徳島 |
| 63.0~67.9% | 福島・千葉・埼玉・静岡・兵庫・岡山・山口・愛媛・高知・大分・宮崎・佐賀・長崎・鹿児島 |
| ~62.9% | 北海道・宮城・東京・神奈川・愛知・京都・大阪・広島・福岡・熊本・沖縄 |
“参考:総務省統計局「特集 今年度実施予定の主要統計調査」”
持ち家は全国的に東北の日本海側で高く、特に秋田では77.3%となっています。逆に賃貸の比率が高いのは、沖縄の55.6%と東京の55%です。
賃貸と持ち家の比率からわかる社会情勢
上記で紹介してきた賃貸と持ち家の統計データから、最近の社会情勢を分析してみましょう。
主に次の2つのポイントについて解説します。
- 都市部では持ち家購入のハードルが高い
- 晩婚化で持ち家がある年齢層に変化
都市部では持ち家購入のハードルが高い
都市部は地方より地価が高いため、土地を購入して家を建てるとなると高額になってしまいます。地方では坪単価が数万円のエリアもありますが、東京では坪単価が100万円を超えることも珍しくありません。
都市部は地方と比較すると賃金が高い傾向にありますが、地方より物価が高かったり、持ち家の購入前に住む賃貸の価格も高かったりと、都市部での生活には費用がかかります。
都市部での持ち家購入はますますハードルが高くなっているため、東京に在住・通勤している人でも、埼玉や千葉など地方エリアにマイホームを建てたいと考えている人もいるでしょう。
関連記事:土地を安く買う10の方法を徹底解説!土地探しから税金対策まで
関連記事:土地の価格の調べ方とは?目的別のおすすめ手法や計算式を紹介
晩婚化で持ち家がある年齢層に変化
結婚して家族が増えることは、家を購入したいと考えるきっかけになるでしょう。
1983年と2018年の年齢別の持ち家比率を比較してみると、20代の持ち家比率は17.9%から6.4%まで下がっています。また、30代の持ち家比率も53.3%から35.9%まで落ち込んでいます。
このように、特に20代~30代の持ち家比率が減少しているのは、晩婚化やライフスタイルの変化が原因といえるでしょう。
一人暮らしであればワンルームの賃貸でも充分暮らすことができるため、結婚して家族が増えることは家を購入したいと考えるきっかけになります。また、「人生100年時代」といわれる現代では、老後の生活を考え住み替えを意識して、賃貸を選択している人も多いようです。
賃貸と持ち家の比較ポイント
紹介した統計データより、1973年から40年以上持ち家のほうが賃貸と比べて比率は高いです。しかし、比率が高いからといって持ち家のほうがよいとは限りません。そこで、次の6つのポイントで持ち家と賃貸を比較しました。
- 資産価値
- 維持費の負担
- 住み替えのしやすさ
- リフォームの自由度
- 老後の生活
- 万が一の備え
それぞれの違いを詳しく解説していきます。
資産価値
賃貸の場合は、どれだけ長く住んでも住む限りは家賃が発生し、資産価値はゼロです。もし30歳から80歳まで50年間賃貸に住んだ場合、ファミリータイプで月10万円程度の物件でも、最低6,000万円がかかります。実際には更新費用、必要であれば管理費や駐車場代なども必要です。
持ち家であれば、住宅ローンを完済できると自身の資産となり、相続もできます。土地を購入して家を建てる場合は、エリアによって価格が大きく異なります。地方エリアで建売住宅あれば2,000万円台で購入することも可能ですが、23区エリア内では建売住宅であっても5,000~6,000万円ほど必要となるでしょう。さらに修繕費用や固定資産税、必要であればローン利息もプラスされます。
維持費の負担
賃貸と持ち家で、それぞれの維持費の負担は次のようになっています。
| 賃貸 | 持ち家 |
| ・家賃 ・管理費 ・共益費 ・家財保険 ・駐車場代(アパート・マンションの場合) |
・住宅ローンの返済 ・固定資産税 ・都市計画税 ・火災や地震の保険料 ・メンテナンスやリフォームの費用 ・修繕積立金(アパート・マンションの場合) ・管理費(アパート・マンションの場合) ・駐車場代(アパート・マンションの場合) |
賃貸の維持費にあたる管理費や共益費は、家賃の5~10%が相場です。住む物件によっては、月の維持費は1万円以下に抑えられるケースもあります。
持ち家の場合、住宅ローンの返済額を賃貸の家賃相当にしても、別途で毎年の固定資産税・都市計画税や各種保険料が必要です。また戸建てだと、10~20年周期で外壁や屋根の塗装などのメンテナンスが必要となります。維持費の負担だけを考えると、持ち家の方がかかりやすいです。
関連記事:住宅ローンはどこに相談すべき?相談窓口の種類と相談する際の注意点
住み替えのしやすさ
賃貸であれば、気軽に住み替えができます。退去の予告は必要で2年の縛りがあるケースが多いですが、新居の敷金・礼金や引越し費用を確保できれば、今よりよい条件のところで新生活を始められます。
持ち家の場合は、住み替えのハードルが高い傾向です。持ち家を売却する際は住宅ローンを完済する必要があります。返済には家の売却金を充てることもできますが、必ず自分の希望額で家を売却できるとは限りません。家の立地や状態によっては売れない可能性もあります。
住宅ローンが残る家の売却については、次の記事も参考にしてください。
関連記事:住宅ローンが残る家の売却方法とは?流れや任意売却についても解説
リフォームの自由度
賃貸でのリフォームは、利用規約で厳しく制限され、壁紙の張り替えでもオーナーの了承が必要となるでしょう。退去する際は、原状回復を求められる場合がほとんどです。原状回復ができない場合、追加で費用を請求されてしまいます。
持ち家のリフォームの自由度は高く、戸建てであれば建築基準法の範囲内で、増改築や間取りの一新も可能です。費用に余裕があれば、一度解体してしまうのもありです。
持ち家が分譲マンションの場合は、専有部分のリフォームができます。構造に影響がでる間取りの変更は許可されていない場合もありますが、床や天井、壁紙を変えてることは問題なくおこなえるでしょう。リフォーム前提で中古マンションを持ち家にする人もいます。
老後の生活
賃貸での生活は、老後で独身になってしまった際に支障がでる可能性があります。孤独死の懸念や毎月の収入、資金不足などが原因で入居審査に通りづらくなる可能性も否めません。
持ち家であれば、いくつになっても誰に気兼ねすることなく住み続けられます。住宅ローンを完済していれば、必要になるのは固定資産税やメンテナンス費用程度のため、賃貸で家賃を払い続けるより負担が軽い場合がほとんどです。収入が年金だけでも生活していけるでしょう。
家の売却相場については、次の記事で紹介している不動産一括査定サイトを利用すると、簡単にわかります。
関連記事:不動産一括査定サイトおすすめランキング16選を比較【2024年3月最新】売却の体験談を掲載!人気サイトの評判や選び方も
万が一の備え
賃貸に家族で住む場合、万が一メインで稼いでいる人が亡くなると、場合によっては家賃の支払いが難しくなってしまうこともあります。
持ち家の場合は、団体信用生命保険を利用した住宅ローンを組んで購入していると、残債がいくら残っていても安心です。団体信用生命保険は、加入者が亡くなった際に住宅ローンの残債がゼロになる保険です。残った家族は、維持費の負担だけで持ち家にそのまま住み続けることができます。
賃貸と持ち家のどちらがおすすめ?
賃貸と持ち家について、それぞれおすすめの人を解説します。家を購入するか迷っている人は、自身がどちらに該当するのかチェックしましょう。
賃貸がおすすめの人
- 気軽に住み替えたい人
- 管理を自身でしたくない人
- 維持費の負担を減らしたい人
結婚してから住み始めた家でも、転勤や子供の進学・独立など、賃貸であればライフイベントごとに住み替えをしやすいです。近所の迷惑な人とトラブルになる場合も、より快適に暮らせるところへの引越しが容易です。
管理はオーナーや管理会社任せで、問題がおきても連絡をすると対応してもらえます。メンテナンス費用も自己負担せず住み続けることが可能です。
持ち家がおすすめの人
- 家を資産としたい人
- 収入が安定している人
- 老後も安心して暮らしたい人
持ち家は一生ものの資産となり、子供や孫の世代にも残せます。将来まとまったお金が必要で融資を受ける際、家は担保になり住宅ローンの返済は実績にもなってくれます。完済できると老後の出費は節約でき、住処探しで困らないでしょう。
また、持ち家は住宅ローンを滞納しないためにも、収入が安定している人に向いています。賃貸であれば、収入が減少したら家賃の低いところへ引っ越すことも容易ですが、持ち家の場合は住み替えが難しいです。
関連記事:【初めての人必見】住宅購入の流れ10ステップを徹底解説!
関連記事:注文住宅を建てる流れと期間を徹底解説!費用や注意点も紹介
持ち家を購入するか迷う人の判断基準
「持ち家を購入したいけど、返済していけるのか不安」「マイホームは欲しいけど、購入するタイミングで悩んでいる」という人も多いのではないでしょうか。
持ち家を購入すべきか判断するために、基準となる次の3つのポイントについて解説します。
- 現在の年齢
- ライフプラン
- 家計の資産状況
3つの判断基準について、それぞれ詳しくチェックしていきましょう。
関連記事:戸建て購入時に確認する17の注意点|新築・中古別にデメリットも紹介
現在の年齢
現在の年齢によって住宅ローンを組む期間も変わるため、年齢は一つの判断基準となります。
2023年現在、住宅ローンの完済年齢は長くても80歳が上限です。35年の長期ローンを組みたい場合、45歳までに申し込まないといけません。定年退職前に完済したい人はさらに申し込み時期が早くなり、30歳頃には購入を決断したほうがよいでしょう。
現在の年齢から具体的な返済プランを作ってみると、家を購入すべきタイミングを見極めやすくなります。
ライフプラン
持ち家では、気軽に立地や間取りの変更ができません。結婚や出産、子供の独立など、家族構成が変わると住みやすい家の条件も変わります。
少しでも長く快適に住めるよう、ライププランを踏まえて購入のタイミングを計りましょう。
家計の資産状況
持ち家の購入にはまとまったお金が必要です。転職や昇給などで世帯年収が上がった、預貯金で住宅ローンの頭金を確保できたなど、ある程度資産に余裕ができれば購入のタイミングといえるでしょう。逆に、子供の教育費などで出費が増加し、資産の余裕がなくなるタイミングは、避けた方がよいでしょう。
購入価格だけでなく維持費も考慮して、常に余裕のある資産状況を維持してください。お金がないからとメンテナンスをおこっていると、劣化が進み想定より早く資産価値が落ちてしまいます。
賃貸と持ち家の選択でよくある疑問
最後に、賃貸と持ち家の選択で、よくある次の疑問について解説します。
- 賃貸と持ち家でどちらがお得?
- 住宅ローンを滞納したらどうなる?
「賃貸か持ち家か」という選択は、これからの人生に大きな影響を及ぼします。納得して選べるよう疑問は解消しておきましょう。
賃貸と持ち家でどちらがお得?
どちらがお得なのかは、これからどのような暮らしをするかで変わります。維持費の具体的な数字を仮定し、30年や50年の長期で累計のシミュレーションをして判断しましょう。まずは現在住みたい地域で、家賃相場や持ち家の購入費用相場を調べてみるとよいです。
持ち家は欲しいがお金に余裕がない場合は、安い家を探すという選択肢も検討してみましょう。日本は世帯数と比較して住宅の数が多く、田舎などでは売却が難しい物件があります。維持費の負担があるため早く手放したい人が、0円でも家を引渡したいと考えています。自治体が運営する空き家バンクを利用してみてください。
住宅ローンを滞納したらどうなる?
住宅ローンの滞納を続けていると、最終的に家は競売にかけられ、住んでいる人は強制退去となります。競売の代金でも完済に不足する額の請求は続き、自己破産も必要になるかもしれません。
持ち家に住み続けるため、滞納しそうなときはすぐに金融機関へ相談してください。一時的な収入減少であれば一定期間の返済額の軽減、長期での収入減少であれば返済期間の延長(30年から35年)などで、滞納を避けられるよう調整するとよいでしょう。もしくは、別の金融機関で借り換えをすると月の返済額が減る可能性もあります。
まとめ
賃貸と持ち家の比率は約4対6で、総務省統計局の「住宅・土地統計調査」によると、40年以上大きな変動はありません。高齢の人ほど持ち家の比率は高まり、全国的に地価の高い都市部では賃貸のほうが多いです。
比率は持ち家のほうが高いとはいえ、自身にとって最適な暮らしができるとは限りません。資産性や維持費、住み替えのしやすさなどで長期的な比較をして、賃貸か購入か決断しましょう。