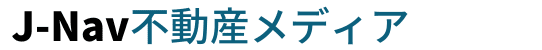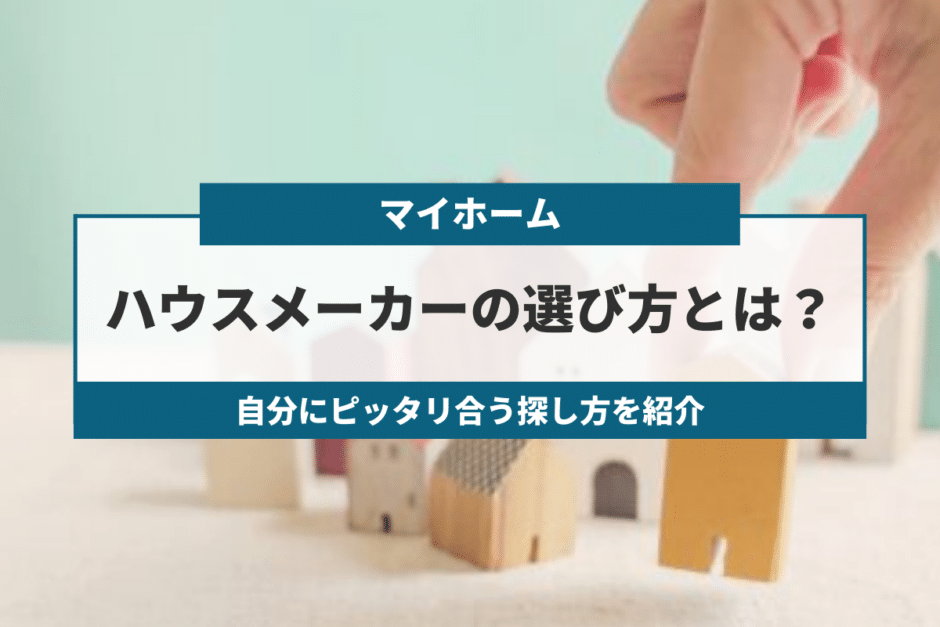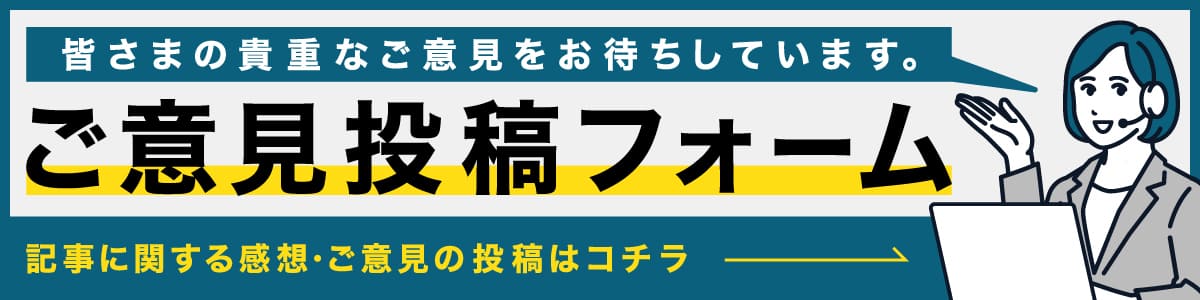※本ページはアフィリエイト広告プログラムによる収益が発生しています
こだわりのマイホームを建てるためハウスメーカーに依頼しようと考えても、どのように選べばよいか迷ってしまう人も多いでしょう。ハウスメーカーには、最寄りの住宅展示場で紹介されているものから、CMや住宅雑誌の広告で見かけるところなど多くの会社があります。
そこで本記事では、ハウスメーカーの選び方や、ハウスメーカーと工務店などとの違いについて解説していきます。マイホームは長期的に住むことになるため、アフターフォローまで満足できるハウスメーカーを選んでください。
 |
名前 | Iさん |
| 物件エリア | 愛知県 | |
| 利用時期 | 2017年 |
※J-Nav不動産メディアでは、ユーザーの生の声をお届けするために、商品・サービスの利用者に直接取材を行っています。

目次
ハウスメーカーの選び方のコツ
ハウスメーカーの選び方で後悔しないコツは次の6つです。
- デザインで選ぶ
- 予算内におさまるか確認
- 工法や構造で選ぶ
- 保証内容で選ぶ
- 担当者は信頼できるか確認
- 住宅の性能で選ぶ
それぞれ詳しく解説していきます。
デザインで選ぶ
まずはハウスメーカーの公式サイトなどで事例を見て、理想のデザインに近いところから候補を絞りこんでください。各社で得意なデザインやスタイルがあります。
もしモダンやフレンチスタイルを得意としているところに、和風のデザインで注文を出しても、十分なノウハウがない可能性があります。初めての家づくりでは、自分で細かく指定するのは難しいため、公式サイトに掲載された実績などからデザインから選んで、担当者に伝えるとスムーズでしょう。
予算内におさまるか確認
次に想定している予算内でマイホームが建てられるのかを確認しましょう。
ハウスメーカーによって、建てる家の予算はある程度決まっています。予算を抑えたい場合は、ローコストなハウスメーカーに依頼をする必要があるでしょう。
同じ条件でも、予算内におさめてくれるハウスメーカーがあるかもしれません。複数社を比較してみましょう。
工法や構造で選ぶ
ハウスメーカーが採用している工法もそれぞれ異なるためチェックしてみましょう。工法によって実現しやすい構造は異なるので、あるハウスメーカーでは実現が難しいと言われた内装であっても、他のハウスメーカーでは可能な場合もあります。
また工法や構造によって、完成までの期間にも影響が出ます。工場生産された建材を多用するものであれば、現場では組み立てが主な作業となるため、短期間での完成が期待できるでしょう。
住宅の性能で選ぶ
住宅の性能とは、耐震性能・断熱性能・気密性能・換気と空調・省エネルギー性能・防水性能・防火性能・耐久性能などの性能のことです。
工法・構造とも関わりは大きく、ハウスメーカーによって住宅の基本性能は違います。
耐震性が高い住宅であれば、地震の際も揺れによる被害を最小限に抑えられるでしょう。気密性や断熱性に優れていると、外からの空気の出入りや熱の伝わりが抑えられて、外気温の影響を受けにくく、室内を一定の温度に保ちやすいです。
性能に関しては、客観的な指標として住宅性能表示制度を活用するとよいでしょう。交付される建設住宅性能評価書による評価は、トラブルがあった際の資料としても使えます。これまでの実績で評価の高い注文住宅を建てているハウスメーカーであれば、性能も期待できるでしょう。
保証内容で選ぶ
ハウスメーカーが提供している保証内容にも注目してみましょう。どれだけ耐久性に優れている高性能な住宅であっても、何十年も住み続けていると経年劣化は避けられません。長期で点検や補修の保証がついていれば、メンテンナンスにかかる費用を節約できるためおすすめです。
保証内容で確認するべき点は次の4つです。
- 保証期間の長さ
- 保証の範囲
- 有償か無償か
- 定期点検の有無
新築の注文住宅では、住宅品質確保促進法によって建物の基礎や構造に関する保証が10年間付いています。
担当者は信頼できるか確認
ハウスメーカー選びでは、担当者が信頼できるかどうかも重要です。話を聞いてくれない、レスポンスが遅い、説明がわかりにくい、要望がなかなか伝わらないなど、何か不安に感じることがあれば、担当者の変更を検討してみてください。
担当者とはマイホームが建つまで長い付き合いになるため、信頼できて相性が合う人を選びましょう。
信頼できる担当者と出会うためには、複数のハウスメーカーに問い合わせをして実際に担当者と話してみるとよいです。何人かの担当者のなかから、一番話しやすくて信頼できると感じた担当者に依頼しましょう。
ハウスメーカーを選ぶ前にしておく3つのこと
ハウスメーカーを選ぶ前に、以下の3つのことを確認しておきましょう。
- 予算決め
- 優先順位や譲れないポイントの整理
- 住宅やハウスメーカーの情報収集
必要な理由や具体的なやり方を詳しく解説していきます。
予算決め
予算を決めずにハウスメーカーを選んでいては、気に入ったところが見つかっても予算オーバーで選び直しになります。そのためマイホーム計画を始める際は、まずいくらまで予算を確保できるのかを決めておきましょう。
決める際に確認するポイントは次の3つです。
- 現在自己資金がいくらあるか(親族からの援助も含む)
- 将来のため残しておきたい資金はいくらか(病気・災害・教育・介護など)
- 住宅ローンの返済は月々いくらまでなら負担にならないか
できるだけ具体的な数字を想定して、シミュレーションをしてください。現在の資金に余裕があるという人も、将来のライフイベントまで見据えて計算してみましょう。
金融機関が提供している住宅ローンのシミュレーションなどを活用し、予算決めをおこなってください。
関連記事:住宅ローンはどこに相談すべき?相談窓口の種類と相談する際の注意点
優先順位や譲れないポイントの整理
予算には限りがあるため、優先順位や譲れないポイントを整理しておきましょう。
デザインや間取り、構造の種類、性能といったものについて希望をすべて列挙し、一緒に住む家族と話し合いをおこない優先順位を決めましょう。誰かに一方的に我慢を強いては、完成後の新生活で不和が生まれやすいです。
なかなか決められない場合は、外構のデザインのようにあとから変更しやすいものに関しては、優先順位を下げるのをおすすめします。間取りや構造など、変更しづらい部分に限定して優先順位を決めてみましょう。
住宅やハウスメーカーの情報収集
事前に情報収集をしておくことによって、理想の住宅の条件や選ぶハウスメーカーの選択肢を増やせます。
ほとんどの人がマイホーム作りは初めてです。知らないことが多くて何から調べればいいかわからないという場合は、住宅情報のポータルサイトなど無料の相談窓口で専門的なアドバイスを受けることも可能です。
住宅展示場やマイホームに関するセミナーなども、各地で無料で開催されています。無料のものは積極的に活用しましょう。
ハウスメーカー選ぶ流れ
実際にハウスメーカーを選ぶ流れは次の3ステップです。
- 資料請求
- ハウスメーカーを訪れる
- 見積もりを依頼
なぜこのステップが必要なのか1つずつ見ていきましょう。
資料請求
情報収集のため、気になるハウスメーカーがあれば資料請求をしましょう。公式サイト上には記載がない情報も知ることもできます。
ゼロからハウスメーカーの情報を集める際は、資料の一括請求ができるサイトを利用するのもおすすめです。
希望の条件を入力するだけで、対応可能なハウスメーカーをリストアップしてくれます。情報の入力は1度で、資料請求の手間もかかりません。
ハウスメーカーを訪れる
次は請求した資料を比較してハウスメーカーを絞り込み、店舗や展示場を訪れましょう。
店舗を訪れる場合は、ハウスメーカーの特徴だけでなく担当者の対応にも注目してください。相談しやすい雰囲気か、わかりやすい説明をしてくれるかなど、担当者との相性も覚えておきましょう。
展示場を見る際は、どのような仕様で建てられているのかの確認をしてください。展示場のデザインや設備は、上位グレードでオプションがフルに適用されている場合がほとんどです。予算内だとどのような内装になるのかも確認しておきましょう。
見積もりを依頼
気になるハウスメーカーを絞り込めてきたら、それぞれ見積もりの依頼を出してください。複数社に見積依頼をすると、各ハウスメーカーが予算内でどこまで条件をクリアできるかを比較することができます。
最終的に、上記で紹介してきた6つのコツで総合的にハウスメーカーを評価して、自分に合うところと工事請負の契約を結びます。契約を結ぶ前であれば費用は請求されないため、納得のいくまでじっくり厳選しましょう。
ハウスメーカーの基礎知識
そもそも注文住宅の依頼はハウスメーカーでよいのでしょうか。その他の選択肢と比較するためにも、まずは基礎知識としてハウスメーカーの相場単価や取り扱う工法、特徴について理解しておきましょう。
ハウスメーカーの相場単価
注文住宅を建てるのに必要な資金は、平均で5,112万円(国土交通省 令和3年度 住宅市場動向調査報告書より)です。実際にかかる費用は依頼先によって大きく変わり、ローコストなハウスメーカーでは坪単価30~50万円でも建てられます。
大手のハウスメーカーでは、坪単価70万円以上を想定しておくとよいです。これらの相場は2023年のもので、直近数年では上昇傾向です。最新情報を収集して予算決めの参考にしましょう。
ハウスメーカーで取り扱っている工法・構造
ハウスメーカーが取り扱っている主な工法は次の5種類です。
| 工法・構造の種類 | 特徴 |
| 木造軸組工法(在来工法) | ・日本の伝統的な工法で柱や梁に木材を使用 ・間取りの自由度が高い |
| 2×4工法(ツーバイフォー) | ・2×4インチで規格化した木材を使用 ・施工期間は短期 |
| 重量鉄骨造 | ・構造の骨組みに厚さ6mm以上の鋼材を使用 ・頑丈だがかかる費用は木材より高額 |
| 軽量鉄骨造 | ・構造の骨組みに厚さ6mm未満の鋼材を使用 ・重量鉄骨造より地盤工事の必要性は低い |
| 鉄筋コンクリート造 | ・柱や梁、壁などに鉄筋コンクリートを使用 ・木造より耐火・耐久性に優れる |
ハウスメーカーによって、どの工法を得意としているかは異なります。特徴から大まかにハウスメーカーを厳選し、希望をどこまで実現できるかは担当者に相談をしましょう。
ハウスメーカーによっては複数の工法・構造を選べます。
ハウスメーカーの特徴
ハウスメーカーとは、次のような特徴をもった注文住宅を建てる業者です。
- 自社で工法の開発・デザイン・施工・販売・メンテナンスなどをすべておこなう
- 対応エリアは広範囲(全国規模のところも)
自社ブランドのデザインで共通建材を多く採用していると、高い品質を維持しながら低コストや短期施工を実現してくれます。
アフターフォロー・メンテナンスにも対応しているため、一生ものの付き合いになることを念頭においてハウスメーカーを選びましょう。
工務店や建築設計事務所との違い
注文住宅の依頼は、ハウスメーカー以外に工務店、建築設計事務所、ビルダーでも可能です。これらはハウスメーカーとなにが違うのでしょうか。
それぞれのメリットデメリットは次のようになっています。
| メリット | デメリット | |
| ハウスメーカー | ・対応地域の広さ ・工場生産の建材仕様で高い品質 |
・デザインは提供ブランドから選択 ・仕様から外れると費用アップ |
| 工務店 | ・地域の特性を理解した設計 ・充実したフォロー |
・質は職人の実力に左右 ・現場での加工に時間 |
| 建築設計事務所 | ・フルオーダーが可能 | ・完成までに時間 |
| ビルダー | ・特定の地域ではハウスメーカーと同等 | ・依頼先によってはフルオーダーに未対応 |
ハウスメーカーと工務店との違い
ハウスメーカーと工務店の主な違いは、営業エリアの広さです。ハウスメーカーは全国展開しているところもあり、地方であっても対応してもらえる可能性は高まります。工務店の対応地域は限定的で、最寄りの市区町村からしか依頼できないのが一般的です。
品質に関しては、自社工場を持っているハウスメーカーだと、建材の品質が安定しています。工務店の場合は職人の実力に左右されることも多く、ハウスメーカーと比較すると現場での加工に時間がかかる可能性が高いです。ただし、工務店ではハウスメーカーよりも細かな要求に対応してもらえることが多いというメリットもあります。
関連記事:ハウスメーカーと工務店の5つの違いとは?それぞれのメリット・デメリットと選び方
ハウスメーカーと建築設計事務所との違い
ハウスメーカーと建築設計事務所の主な違いは、デザインの自由度の高さです。ハウスメーカーは複数のラインナップから大まかなデザインを選ぶのに対し、建築設計事務所はフルオーダーで家づくりが可能です。
マイホーム作りをとことんこだわりたいという人は、自由度が高い建築設計事務所に依頼したほうが希望をかなえやすいでしょう。しかし、ゼロから設計するため完成までに時間がかかります。また、施工は別途工務店への依頼が必要なところもあります。
ハウスメーカーとビルダーとの違い
ハウスメーカーとビルダーの主な違いは事業の規模です。ビルダーはハウスメーカーと工務店の中間的な立ち位置となっています。特定の地域にしか対応できなくとも、自社工場を構えて質の高い建材を供給しているところもあります。
ビルダーは設計から施工までを一貫でおこなっているため、注文の際も細かな融通が利きやすい場合が多いです。
ハウスメーカーに関するよくあるQ&A
最後に、ハウスメーカーで注文住宅を建てる際によくある疑問を、Q&Aで解説していきます。大金が動き容易に取り返しはつきませんので、不安材料はできるだけ解消しておきましょう。
よくある失敗例は?
ハウスメーカー選びでは、次のような失敗例があります。
- 他社と見積りを比較せず予算が想定より高額になってしまった
- 担当者が希望を反映させてくれない
- 採用している工法・構造では希望の間取りを実現できない
- 担当者と連絡がつかない
- 保証を適用させてくれない
- 建築中に倒産
失敗例の中には、完成から数年後に問題が発覚するケースもあります。100%リスクを回避する方法はありませんが、慎重にハウスメーカー選びをおこない、多少時間がかかっても担当者との相性まで見極めることが大切です。
関連記事:戸建て購入時に確認する17の注意点|新築・中古別にデメリットも紹介
住み始めるまでの期間は?
ハウスメーカーに相談してから住み始めるまでの期間は、8~16ヵ月が目安です。建築だけで3~6ヵ月、完成から引渡しまでで1ヵ月程度ですが、建築プランの作成は、話がまとまらなければ期間は大幅に延びてしまいます。また期間は、土地探しまで依頼するかどうかでも変わります。
期間は長期でかかるものと覚悟しておかないと、中途半端に妥協をして不満が一生残るかもしれません。まずは予算決めや優先順位の整理、ハウスメーカーの情報収集から始めましょう。
関連記事:【初めての人必見】住宅購入の流れ10ステップを徹底解説!
関連記事:注文住宅を建てる流れと期間を徹底解説!費用や注意点も紹介
【体験者インタビュー】ハウスメーカーの比較経験がある方に実態を聞いてみた
家を建てたいと考えるようになってから、どのように候補のハウスメーカーを探しましたか?





営業マンの対応にはどのような差がありましたか?





予算の設定はどのように行いましたか?また、実際のコストは予算内で収まりましたか?





まとめ
ハウスメーカーの選び方で、実現できる注文住宅やかかる費用、将来の保証に差が出ます。同じ条件で相談をしても、複数社で比較をしないと、どこが理想に近いのは判断ができません。
本記事で紹介してきた6つの選び方のコツや3つの事前準備、基礎知識を参考に、自身に合うハウスメーカーを選んでください。工事請負の契約を結ぶまでは無料ですので、資料の一括請求ができるサイトも活用し、気になるところへ気軽に相談しましょう。